顔認証を支えるキーテクノロジー:知っておくべき技術要素とは?
- Yukaringo

- 2025年6月12日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年10月22日

顔認証を支えるキーテクノロジー:知っておくべき技術要素とは?
※本記事は、アビココ株式会社が提供するサービスに関連する内容を含みますが、読者の皆さまに有益な情報をお届けすることを目的として執筆しています。
顔認証システムの導入を検討中のIT担当者の皆さん、技術選定で迷っていませんか?
一見シンプルに見える顔認証技術ですが、実際には複数の高度な技術が連携して動作する「技術の複合体」です。スマホで顔をかざしてロック解除するあの便利な機能も、カメラセンサーから認証アルゴリズムまで、様々な技術要素が組み合わさって実現されています。
「顔認証システムを導入したいけど、どの技術を選べばいいかわからない」「ベンダーの提案を技術的に評価したい」そんな課題を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、顔認証システムを選ぶ際の「技術的な目利き」ができるよう、顔認証技術の構成要素から最新トレンドまで、詳しく解説していきます。技術的な背景を理解することで、自信を持ってシステム選定ができるようになるはずです。
顔認証技術の構成要素:実は4つのパーツが連携プレーしてます
1. カメラセンサー:顔を「見る」技術
顔認証の入り口となるカメラセンサー。「ただのカメラでしょ?」と思うかもしれませんが、実は3つのタイプがあるんです。
RGB カメラ(普通のカメラ)
一般的なカラーカメラ
コストは安いけど、照明の影響を受けやすい
写真によるなりすましに弱い
赤外線カメラ
暗闇でも認識可能
表面温度も検知できる(最近の体温チェック機能付きはこれ)
写真攻撃に対する防御力が高い
3D カメラ(深度センサー付き)
立体的な顔の形状を取得
指紋認証に匹敵するレベルの精度を実現
iPhone の Face ID がこの方式
2. 顔検出技術:人混みの中から「顔」を見つける
カメラで撮った画像から「どこに顔があるか」を見つける技術です。
Haar-like 特徴量
古典的だけど軽量で高速
単純な環境では今でも活用されている
DNN(Deep Neural Network)
AI を使った高精度な顔検出
角度や表情が変わっても検出可能
YOLO(You Only Look Once)
リアルタイム処理に特化
複数の顔を同時検出できる
3. 特徴抽出アルゴリズム:顔を「数値化」する技術
検出した顔から、その人固有の特徴を数値化します。ここが認証精度の要となる部分。
LBPH(Local Binary Patterns Histograms)
軽量で処理が早い
基本的な特徴抽出に適している
FaceNet
Google が開発した深層学習ベースの手法
顔を高次元ベクトルで表現
ArcFace
最新の深層学習手法
世界的なベンチマークテストで高い精度を誇る
4. 照合・認証アルゴリズム:「本人かどうか」を判定
抽出した特徴量を使って、登録済みの顔データと照合します。
SVM(Support Vector Machine)
機械学習の古典的手法
少ないデータでも学習可能
k-NN(k-Nearest Neighbor)
最も近い特徴量を持つデータを探す
シンプルで理解しやすい
DeepFace
Facebook(現 Meta)が開発
人間の認識率に匹敵する精度
3D 顔認証 vs 2D 顔認証:立体か平面か、それが問題だ
ビジュアルベース(2D認証)と、IRベース(3D認証)の2つの方式がある顔認証。どちらを選ぶべきでしょうか?
2D 顔認証の特徴
コスト:安価で導入しやすい
処理速度:高速処理が可能
弱点:写真によるなりすましに弱い、照明の影響を受けやすい
3D 顔認証の特徴
精度:2次元の場合よりも劇的に正確さが向上
セキュリティ:立体情報により写真攻撃を防げる
コスト:高価だが、セキュリティ要求が高い場合は必須
選択の目安
出退勤管理程度なら 2D で十分
金融機関やセキュリティ重視なら 3D 必須
マスク着用が多い環境では 3D が有利
リアルタイム認識技術とエッジ AI:クラウドかエッジか
顔認証の処理をどこで行うかも重要な選択肢です。
クラウド処理
メリット:高性能な処理、最新アルゴリズムの活用
デメリット:通信遅延、プライバシーの懸念
適用場面:入退室管理、イベント会場
エッジ処理
メリット:高速レスポンス、プライバシー保護
デメリット:端末の処理能力に依存
適用場面:スマホ認証、セキュリティ重視の環境
既に様々な業界で、安全性やセキュリティの向上、作業の効率化などの用途で活用され、多くのメリットをもたらしていますが、処理方式の選択は用途に応じて慎重に検討しましょう。
顔認証技術のセキュリティ対策:なりすまし防止が鍵
Liveness Detection(生体検知)
写真や動画を使ったなりすましを防ぐ技術です。
パッシブ方式
特別な動作を要求しない
ユーザビリティが高い
3D 情報や微細な動きを検知
アクティブ方式
「まばたきして」「首を振って」などの指示
確実性は高いがユーザーに負担
暗号化・匿名化技術
顔のデータをそのまま保存するのではなく、暗号化やハッシュ化して保存。万が一データが漏洩しても、元の顔データを復元できないようにします。
テンプレート保護
顔の特徴量を暗号化して保存
逆算して顔画像を復元できない形式
分散保存
顔データを複数の場所に分散保存
一箇所が侵害されても全体は安全
技術トレンド:顔認証×〇〇の融合が進んでます
マルチモーダル認証の実用化事例
顔認証単体ではなく、複数の認証方式を組み合わせる動きが実際に始まっています。
実用化済み:顔×虹彩認証
大手セキュリティベンダーが「顔・虹彩マルチモーダル生体認証」を実用化
カメラを見るだけで高精度な本人確認を実現
国際的な導入実績も蓄積されている
開発中・検討段階:顔×音声認証
声紋と顔の両方で認証する技術
バンキングアプリやコールセンターでの活用が期待される
まだ大規模な商用導入事例は限定的
スマートデバイス連携の現状
IoT デバイスとの連携が実際に製品化されています。
実用化済み:スマートロック連携
顔認証対応のスマートロック製品が市場に登場
顔認証と指紋認証の両方に対応した製品も存在
個人宅での導入が拡大中
開発段階:総合セキュリティシステム
監視カメラと顔認証の統合システム
不審者検知や入退室管理への応用
技術的には可能だが、プライバシー配慮が課題
端末内処理(エッジAI)の進化
従来は顔認証の処理をクラウド(インターネット上のサーバー)で行っていましたが、最近では端末内で直接処理できるようになりました。
エッジAIとは
端末(スマホやカメラ)の中で直接AI処理を行う技術
インターネットに接続しなくても認証が可能
プライバシー保護と高速処理を両立
身近な例
スマートフォンでの顔認証(iPhone Face IDなど)
防犯カメラでのリアルタイム検知
オフラインでも動作する入退室管理システム
これにより、通信が不安定な環境でも安定した顔認証が可能になっています。
まとめ:自社に合った技術を選ぶための視点
技術選択のチェックリストを用意しました。導入検討時にぜひ活用してください。
要件整理のチェックリスト
セキュリティレベル
[ ] 金融レベルの高セキュリティが必要か?
[ ] なりすまし対策は必須か?
[ ] プライバシー保護の要求レベルは?
運用環境
[ ] 屋内?屋外?照明条件は?
[ ] マスク着用者が多い環境か?
[ ] 同時認証する人数は?
コスト・性能
[ ] 初期導入コストの上限は?
[ ] 運用コストの想定は?
[ ] 認証速度の要求は?
技術仕様
[ ] 2D で十分?3D が必要?
[ ] クラウド処理?端末内処理?
[ ] 既存システムとの連携は?
これらの要件を整理したうえで、ベンダーと技術的な議論ができれば、きっと自社にぴったりの顔認証システムを選べるはず。
アビココに相談してみませんか?
もし「やっぱり専門家に相談したい」「技術選定で迷っている」という場合は、アビココにご相談いただければ、技術的な観点から最適な選択肢をご提案いたします。お気軽にお声かけください。
アビココの会社案内や導入実績資料はこちらからご覧いただけます。
関連記事
顔認証システムの仕組みや導入事例、AI技術の活用方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください:




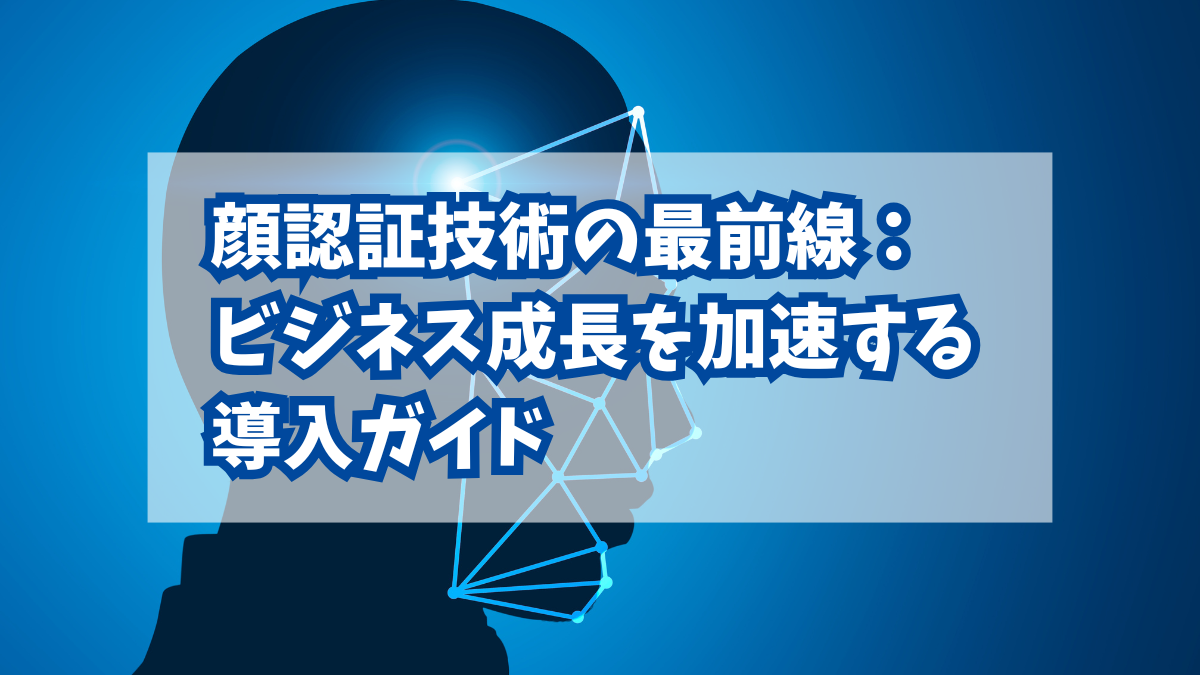

コメント