家族が不在でもデイサービス送迎は可能?事業者がとるべき対応と同意書の活用法
- Yukaringo

- 2025年9月4日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年9月8日

家族が不在でもデイサービス送迎は可能?事業者がとるべき対応と同意書の活用法
※本記事は、アビココが提供するサービスに関する広告・PRを含みます。
はじめに
「あれ?今日もお迎えの時間にご家族がいらっしゃらない…」
「働き盛りのご家族だと、送迎時間に不在なのは当たり前よね」
こんな場面、デイサービス事業者の皆さまも経験ありませんか?
でも悩ましいのが…
「家族が不在でも送迎していいの?」
「万が一事故やトラブルが起きたらどうなる?」
本記事では、厚生労働省や公的機関が示す指針に基づいて、制度的な考え方と現場対応のポイントを整理します。
結論:家族不在でも送迎は可能。その条件とは?
制度上、送迎の対象範囲は「利用者が居宅に帰着し、安全な状態と認められるまで」とされています。したがって、家族が不在でも、利用者が安全に自宅に入れる状態であれば、送迎は可能です。
ただし、認知症、転倒リスク、服薬・火元・鍵管理などの要因がある場合は、以下の対応が不可欠です:
ケアプランや個別サービス計画で必要性を明示する
家族または関係者との事前の合意(同意)を得る
必要に応じて訪問介護等との連携体制を組む
制度上のポイントを3つに整理
1. 送迎は「玄関まで」に限られない
「玄関で引き渡せば終了」という考えではなく、安全な状態が確認されるまでが送迎の責任範囲です。場合によっては、更衣・移動の見守りなどの短時間の居宅内介助が含まれます。
2. 居宅内介助は条件付きで可能
平成27年度介護報酬改定Q&Aでは、「送迎時の居宅内介助を通所介護に含められる可能性がある」と明記されています。ただし、必要性の個別判断とケアプランへの明文化が前提です。
3. 自宅以外への送迎や有償送迎は注意が必要
通所介護の送迎は、原則として「居宅―事業所間」です。
自宅以外(例:病院、家族宅など)への送迎が必要な場合は、自治体の運用に従う必要があります。
また、有償で送迎を提供する場合には、道路運送法上の許可・登録が必要になることがあります。
事業者が整えるべき3つの実務対応
項目 | 内容 |
1. アセスメント | 家族の在宅状況や緊急連絡先、鍵の管理・認知・身体状況・服薬・火元のリスク等を把握 |
2. リスク評価 | 例:認知症進行、転倒リスク、服薬管理の不安などを「要注意」とし、短時間の独居が可能なケースを「許容」とするなど判断基準化 |
3. 同意(事前合意)の文書化 | 鍵の取り扱いや不在時対応など、責任範囲・対応フロー・役割分担を明文化。訪問介護等との連携も明記。 |
同意書に入れるべき内容(例)
基本情報:対象日時、緊急連絡先、鍵の保管・管理方法など
対応ルール:呼び鈴回数、待機時間、再訪フロー、連絡優先順位など
責任分担:事業所と家族それぞれの役割、訪問介護等との連携方法
中止条件:体調不良、悪天候、安全確認不可の際の判断基準
運用時のポイント
詳細な送迎記録の保持(例:到着・出発時刻、居宅内の様子、連絡内容、判断の根拠など)
定期的な見直しの実施(例:3か月ごとに状態変化や家族状況、合意内容を儀的に見直す)
職員研修の充実― 認知症・転倒予防・緊急対応・情報連絡体制・道路運送法の基礎等
Q&A:よくあるご質問
Q1. 家族が急に不在になった場合は?
→ 事前フローに従い、「安全最優先」で対応。必要に応じて訪問介護との連携や帰所判断を。常に判断内容とその経緯を記録。
Q2. 同意書があれば責任は免除される?
→ いいえ。安全配慮義務は事業者にあります。同意書は「同意の範囲や手順を明確化する」目的のもとで活用するツールとして位置づけましょう。
Q3. 鍵の管理はどこまでやっていい?
→ 鍵の授受や開錠が特定の法規で許可されているわけではありません。必要性の判断、ケアプランへの明記、家族の同意、記録、本当に必要な範囲に限定することが重要です。
Q4. 自宅以外への送迎は可能?
→ 原則は「居宅⇄事業所」です。自宅外への送迎が必要な場合は、「自治体の運用に従う」「法的な許可の確認」が必要です。有償送迎には道路運送法の許可が必要になる場合があります。
まとめ
家族不在でも送迎は可能:重要なのは「安全な状態の確認」
居宅内介助は制度上可能だが、必要性の判断と計画と合意が前提
同意書の整備・連携・記録・見直しが安全運営の鍵
自宅外送迎や有償送迎は、行政や法令の確認が必要
アビココ「ナビれる」で送迎業務をもっと効率化!
「家族不在時の送迎対応、もっと安全かつスムーズに行いたい」
「ルート調整の負担を減らしたい」
という事業者様には、アビココの AI 自動配車システム「ナビれる」がおすすめです:
最適ルートを瞬時に自動作成
急な変更や組み替えにも対応
詳しくはナビれる公式サイトへ
参考文献
家族対応は大切なテーマですが、送迎全体の効率化やリスク管理の視点も不可欠です。その包括的な解説はこちらの記事でご紹介しています。




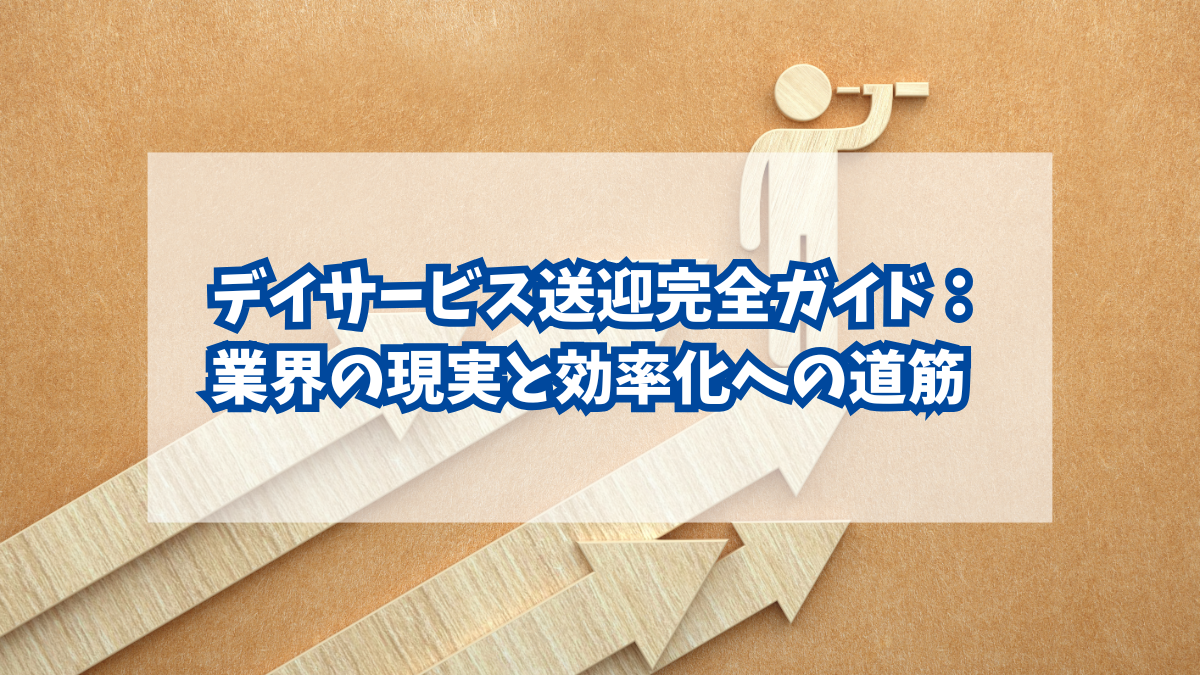



コメント