【2025年最新版】デイサービス送迎で必須!アルコールチェック義務化の対象・方法・罰則まとめ
- Yukaringo

- 2025年8月25日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年9月8日

【2025年最新版】デイサービス送迎で必須!アルコールチェック義務化の対象・方法・罰則まとめ
※本記事はアビココが提供するサービスに関する広告・PRを含みます。
この記事でわかること
2022年以降、道路交通法施行規則の改正により、デイサービス送迎業務でもアルコールチェックが義務化されました。この記事では、介護事業所が押さえておくべき以下のポイントを整理しています。
アルコールチェック義務化の背景と目的
対象となる事業所の条件
チェック方法(目視/アルコール検知器)
記録・保管のルール
違反時の罰則
効率的に運用するためのコツ
今回は、デイサービス事業所の送迎におけるアルコールチェック義務化について、どこよりもわかりやすく解説していきますね。
なぜアルコールチェックが義務化されたの?
そもそも、なぜ今になってアルコールチェックが厳しくなったのでしょうか。
実は、近年の飲酒運転による重大事故の増加が大きなきっかけになっています。特に業務中の飲酒運転事故が社会問題となり、「これは何とかしないと」という社会的な要請から、2022年4月1日に道路交通法施行規則第9条の10が改正されました。
デイサービスの送迎車も例外ではありません。利用者様の命をお預かりしている以上、安全運転はもちろんのこと、その前提となる体調管理も事業者の重要な責任というわけです。
どんな事業所が対象になるの?
「うちの事業所は対象になるの?」と気になりますよね。対象となるのは、安全運転管理者を選任する義務がある事業所です(道路交通法第74条の3第1項・第4項に規定)。
具体的には以下の条件のいずれかに該当する事業所:
乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
その他の自動車を5台以上使用している
デイサービスでよく使われる送迎車(ハイエースなど)は乗車定員が10人以下のことが多いので、「5台以上」の基準で判断することが多いでしょう。
ただし、車両台数の数え方にはちょっとしたコツがあります:
リース車も含む
業務で使用するマイカーも含む
自動二輪車(50cc超)は0.5台として計算
「え、リース車も入るの?」と驚く方も多いのですが、名義に関係なく、実際に業務で使用する車両すべてがカウント対象になります。
アルコールチェックの具体的な内容
では、実際にどんなチェックをすればいいのでしょうか。2段階に分けて実施されています。
第1段階(2022年4月1日~):目視等による確認(道路交通法施行規則第9条の10第6号・7号)
運転前と運転後に、ドライバーの酒気帯びの有無を目視等で確認
確認内容を記録し、1年間保管
安全運転管理者が直接確認することが原則
「目視等って何?」と思うかもしれませんが、要するに顔色や様子、におい、受け答えの様子などを総合的に判断することです。
第2段階(2023年12月1日~):アルコール検知器使用の義務化(道路交通法施行規則第9条の10第6号・7号)
運転前と運転後にアルコール検知器を使用した確認が必須
検知器の常時有効保持(故障していないか定期点検)
検知結果の記録・保管
当初2022年10月から始まる予定でしたが、アルコール検知器の品薄状態などを受けて延期され、2023年12月からスタートしています。
アルコール検知器の選び方
「どんな検知器を買えばいいの?」というのも気になるポイントですね。
法的には「国家公安委員会が定める要件を満たすもの」となっていますが、具体的には:
呼気中アルコール濃度を測定できるもの
一定の精度を有するもの
呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器(道路交通法施行規則第9条の10第6号に基づく国家公安委員会告示)
市販されているアルコール検知器であれば、基本的にはこの要件を満たしています。価格は数千円から数万円まで幅広くありますが、業務用としては以下を検討するといいでしょう:
一定の精度と耐久性がある
メンテナンスが容易
複数人が使いやすい形状
記録機能がある(あれば便利)
最近はアルコールチェック記録アプリと連携できる製品もあり、記録・保管業務の手間削減につながります。
安全運転管理者の役割
アルコールチェックの実施責任者は安全運転管理者です。この方の主な業務は:
ドライバーの酒気帯び確認
運転日報の管理
運転者への安全運転指導
車両の点検・整備管理
運転計画の作成
「管理者って誰がやるの?」という疑問もありますが、事業所の中から選任する必要があります。ただし、以下の要件があります:
※要件:20歳以上、運転経験2年以上、過去2年以内に一定の違反歴がないこと。
記録・管理のルール
アルコールチェックの結果は必ず記録し、1年間保管する必要があります。
記録項目は警察庁が定めています。
確認者名
運転者名
車両ナンバー
確認日時
確認方法(検知器使用か/対面か)
酒気帯び有無
指示事項
「毎日の記録が面倒...」という声もよく聞きますが、最近ではデジタル化による効率化も進んでいます。スマホアプリや専用システムを活用すれば、記録の手間を大幅に削減できますよ。
違反した場合の罰則
「もし守らなかったらどうなるの?」という不安もありますよね。
道路交通法違反として以下の罰則が科せられる可能性があります:
安全運転管理者を選任しなかった場合:50万円以下の罰金
届出を怠った場合:5万円以下の罰金
アルコールチェック未実施:道路交通法違反
万が一事故が発生した場合、民事責任・社会的信用失墜にも直結するため、しっかりとした対策が不可欠です。
よくある質問(FAQ)
Q. パートタイムドライバーも対象?
A. はい、雇用形態に関係なく、事業所の車両を運転する人すべてが対象です。
Q. 管理者が不在のときはどうする?
A. 副安全運転管理者や代理の者が確認を行います。事前に体制を整備しておきましょう。
Q. 検知器が故障したら?
A. 故障時は目視等による確認に戻します。ただし、速やかに修理・交換が必要です。
効率的な運用のコツ
アルコールチェックを効率的に運用するためのポイントをお伝えします:
1. システム化を検討する
手書きでの記録・管理は手間がかかります。専用アプリやクラウドシステムを導入すれば、記録の自動化や一元管理が可能になります。
2. ルーティン化する
毎日決まった時間、決まった場所で実施することで、忘れ防止になります。朝礼時に組み込むのも効果的です。
3. スタッフ教育の徹底
アルコールチェックの目的と重要性をスタッフ全員が理解することが大切です。単なる「やらされ仕事」にならないよう、定期的な研修を実施しましょう。
4. 代理体制の整備
安全運転管理者が不在のときでも対応できるよう、複数人が確認業務を行えるようにしておきます。
デジタル化で業務効率化
「記録作業が負担...」「管理が大変...」そんな課題を抱えている事業所には、デジタル化がおすすめです。
最近では、アルコールチェックと連携できる総合的な車両管理システムも登場しています。単にアルコールチェックだけでなく、送迎ルートの最適化や配車管理まで一元化できれば、事業所全体の効率化につながります。
送迎業務をもっと効率化したい事業所様へ
アルコールチェックの管理と合わせて、送迎業務全体の効率化をお考えでしたら、アビココの「ナビれる」をぜひご検討ください。
AI自動配車システム「ナビれる」なら、複雑な送迎ルートを自動で最適化し、配車作業の負担を大幅に軽減できます。アルコールチェック記録の管理機能も搭載予定で、送迎業務のトータルサポートが可能です。
詳しくはナビれる公式サイトへ
送迎業務の「困った」を「できた!」に変える、新しい働き方を提案いたします。
参考文献
法令対応はもちろん欠かせませんが、送迎業務全体を効率的に運営する視点も必要です。業界の現実と改善策をまとめた記事はこちらです。




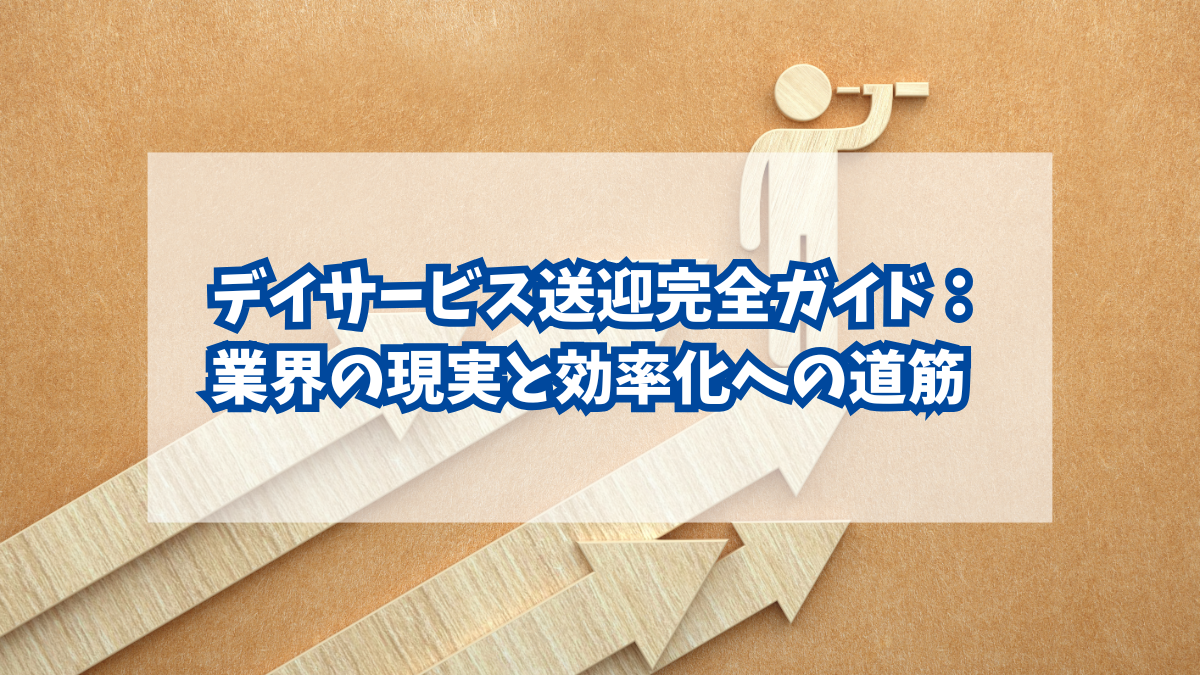



コメント