どこまで送迎していい?デイサービスの送迎範囲と対応事例【2024年度対応】
- Yukaringo

- 2025年8月8日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年9月8日
※本記事は、アビココが提供するサービスに関する広告・PRを含みます。

どこまで送迎していい?デイサービスの送迎範囲と対応事例【2024年度対応】
デイサービス事業所の運営において、「どこまで送迎できるのか」は利用者やその家族からの相談も多く、非常に重要な判断ポイントです。ただ、法律で明確な距離や時間の基準が定められていないため、どう対応すればよいか迷ってしまう事業所も少なくありません。
この記事では、送迎に関する法的なルールや2024年度(令和6年度)の介護報酬改定での変更点、実際の対応事例までをわかりやすく解説します。
送迎に関する法律上のルール
距離や時間に関する上限は明確に決まっていない
現在の制度では、「デイサービスの送迎は○km以内」などの明確な距離や時間の制限は定められていません。つまり、法律的には送迎範囲は事業所の判断に任されているのが実情です。
ただし、現実的には「送迎にかかる時間や労力」「職員の勤務時間」「事故のリスク」などを考慮して無理のない範囲を設定する必要があります。
送迎は基本報酬に含まれている
通所介護や通所リハビリなどのサービスでは、送迎は基本報酬に含まれているサービスです。利用者の自宅と事業所間の送迎は、原則としてサービスの一環として提供することが求められます。
送迎を行わない場合の「送迎減算」
以下のような場合には、介護報酬の「送迎減算」が適用されます。
利用者が自力で通所する場合
家族が送迎する場合
事業所のスタッフが送迎を行わない場合
ただし、「同一建物等減算」が適用されている利用者については、すでに報酬が減額されているため、追加で送迎減算が適用されることはありません。
2024年度(令和6年度)介護報酬改定での変更点
より柔軟な送迎が可能に
2024年度の介護報酬改定では、以下のような送迎の柔軟化が認められました。
住民票と異なる実際の居住地への送迎が可能に
他の通所系介護サービスや障害福祉サービスを利用する人との共同送迎が可能に
実務への影響
この改定により、たとえば以下のような対応が可能になります。
利用者が住民票を移していない家族宅に一時的に居住している場合でも、その住所へ送迎できる
他事業所の利用者と一緒に送迎車に乗せることで、効率的なルートの組み立てが可能
送迎範囲を決める際のポイント
1. 安全面への配慮
長時間の運転は事故リスクやドライバーの負担が増えます
利用者にとっても長時間の移動は身体的負担になります
運転手の労働時間や休憩の確保も大切です
2. 経営面のバランス
ガソリン代や車両維持費、人件費などコストがかかります
他の利用者への影響(送迎時間の遅れなど)も考慮が必要です
3. 地域の事情
渋滞の多いエリア、山間部など交通事情も考慮が必要です
近隣事業所の送迎範囲や、地域の公共交通の有無も影響します
送迎範囲外の利用者への対応事例
● 家族送迎との併用
事業所の送迎可能エリア内の場所(駅やスーパーの駐車場など)まで家族が送迎し、そこから事業所が引き継ぐ方法です。
● 送迎なしでの利用(送迎減算を適用)
利用者がタクシーや自家用車で自力通所する場合、送迎サービスを提供しない分、介護報酬が減額されます。
● 条件付き送迎
特定の曜日だけ送迎する
月に数回のみ送迎する
合乗(他の利用者と同乗)が可能な場合のみ送迎する
このような形で、事業所の負担を軽減しつつ柔軟に対応する例も増えています。
運営上の注意点
● 送迎記録の管理
送迎を行った・行わなかったという記録は、介護報酬の算定の根拠になるため、正確に記録することが必要不可欠です。
● 契約時の説明と同意
送迎範囲や送迎の条件などは、契約時にしっかり説明し、文書で確認・同意を取ることが重要です。
● 労働時間の管理
送迎業務はスタッフの出勤・退勤時間に関わるため、労働基準法に則ったシフト管理が求められます。
複数事業所による共同送迎について
介護報酬改定により、2024年度から以下の点が認められました:
他の通所サービス・障害福祉サービスとの共同送迎
実際の居住地(住民票でなくてもOK)への送迎
まとめ:送迎範囲は「自由」だけど「慎重に」
デイサービスの送迎範囲に法的な上限はないとはいえ、運営上は下記のようなバランスが大切です:
利用者の安全
スタッフの負担や労働時間管理
経営的な効率
契約・同意の明確化
制度改定の把握と適切な運用
送迎業務の効率化には「ナビれる」もおすすめ!
送迎業務にお悩みの事業所には、アビココが開発したAI自動配車システム「ナビれる」をご紹介します。
モニター募集実施中!
先着100事業所限定で12ヶ月無料モニター
初期費用なし・1台2,500円/月(追加料金なし)
利用者・スタッフ情報の初期登録も無料代行
詳細・お申し込みはこちら↓
送迎範囲の線引きは事業者ごとに悩ましいテーマですが、実は業務全体の仕組みを見直すことが効率化につながります。その全体像は、こちらの記事でご紹介しています。





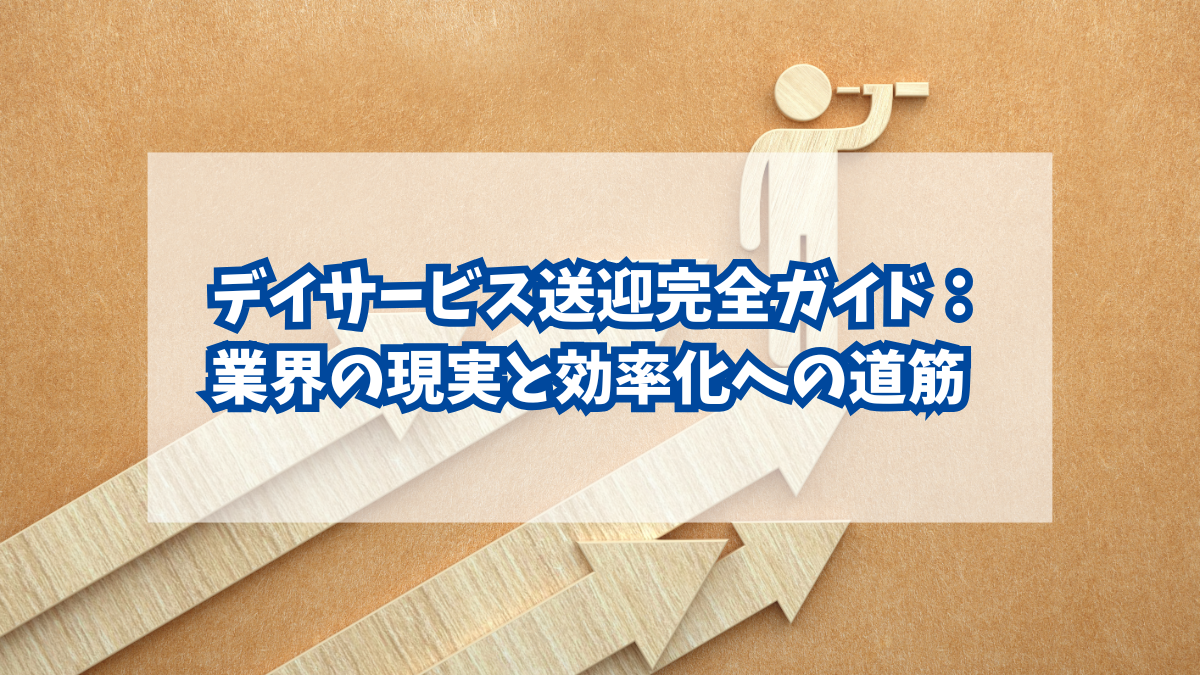



コメント