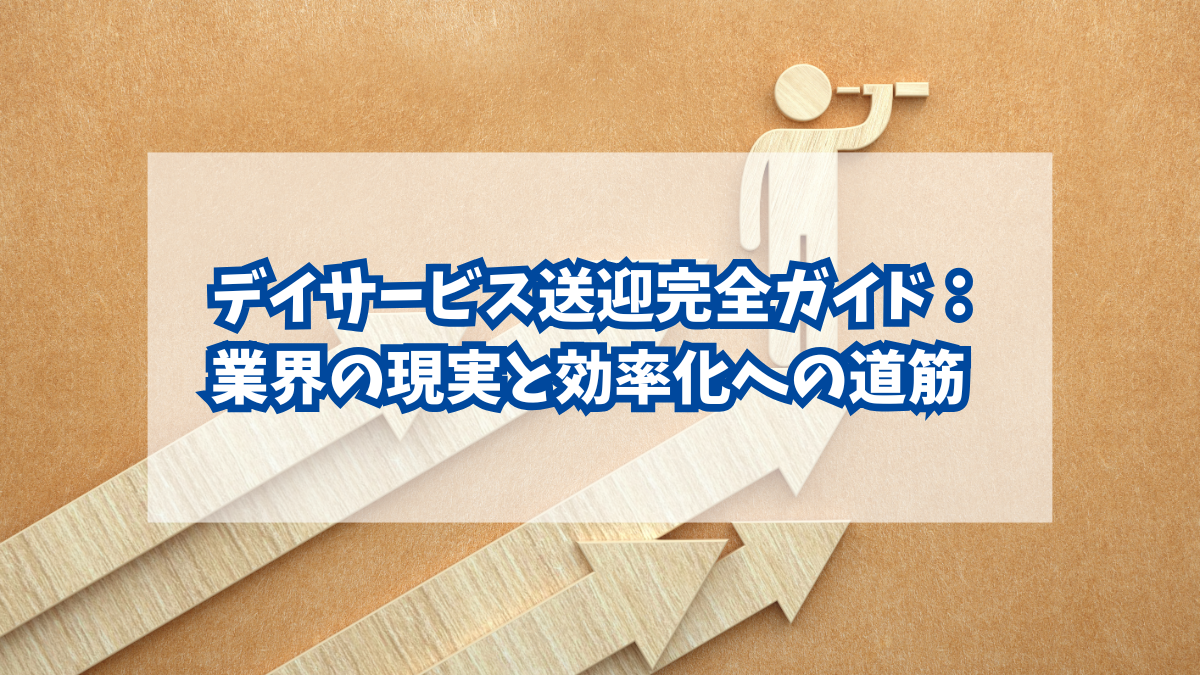デイサービス送迎マニュアル作成ガイド|最新法令・安全装置・事故対応を網羅
- Yukaringo
- 15 時間前
- 読了時間: 5分
デイサービス送迎マニュアル作成ガイド|最新法令・安全装置・事故対応を網羅
※本記事は、アビココ株式会社が提供するサービスに関連する内容を含みますが、読者の皆さまに有益な情報をお届けすることを目的として執筆しています。
デイサービスにおける送迎業務は、単なる移動手段ではなく、利用者の命と尊厳を守り、ご家族との信頼関係を築く重要な業務です。
近年は、送迎中の事故や車内置き去り事案を受けて、国による安全対策の強化やガイドライン整備が進んでいます。
特に、2023年4月から送迎用バス等への置き去り防止支援装置の設置が制度化されるなど、送迎業務を「経験や慣れ」だけに頼る運用は、リスクが高まっています。
本記事では、最新の公的指針や実務慣行を踏まえた「デイサービス送迎マニュアル」に盛り込むべき内容を、現場で使える形で整理・解説します。
1. なぜデイサービスに送迎マニュアルが必要なのか
送迎マニュアルの整備は、単なる業務効率化ではありません。事業所とスタッフ、そして利用者を守るための「安全装置」です。
事故防止と安全確保
乗降時の転倒・転落
車内での体調急変
置き去り・降車漏れ
こうしたリスクは、明確な手順と確認ルールによって大幅に減らすことができます。
サービス品質の標準化
担当者による対応のばらつきを防ぐ
新人スタッフでも一定水準の対応が可能
「誰がやっても同じ安全レベル」を実現
コンプライアンスと事業所防衛
道路交通法
厚生労働省の事故防止ガイドライン
自治体指導・監査への備え
マニュアルは、「もしも」の際に事業所を守る証拠資料にもなります。
2. 送迎マニュアルに必ず盛り込むべき5つの項目
① 運行前の準備・車両点検
安全な送迎は、出発前の確認から始まります。
車両点検
タイヤ(空気圧・損傷)
ブレーキの効き
ライト・ウインカー
燃料残量
安全装置の確認
置き去り防止支援装置(設置している場合)の作動確認
※介護送迎車両は法的義務対象外の場合もありますが、 ヒヤリハット防止の観点から導入・運用が強く推奨されています。
持ち物確認
緊急連絡先名簿
携帯電話
救急セット
嘔吐処理セット
予備の紙パンツ・手袋 など
ドライバーの健康管理
体調不良・睡眠不足の有無
アルコールチェック(※安全運転管理者選任義務がある事業所の場合)
※アルコールチェックや記録保存は、安全運転管理者を選任している事業所に義務が生じるケースがあります。自事業所の該当有無を確認したうえで、マニュアルに明記しましょう。
② 乗降・移動介助の基本手順
乗車時
車椅子ブレーキ・フットレスト確認
段差・足元への声かけ
ドア開閉時の巻き込み・挟み込み防止
走行中
急発進・急ブレーキ・急ハンドルの禁止
利用者同士の接触・体調変化への注意
車内での適切な声かけ
降車時
シートベルト・車椅子固定解除の確認
安全な場所への誘導
可能な範囲で家族・同居人への引き継ぎ(※法令上の義務ではなく、安全確保のための実務推奨)
③ 事故・緊急時の対応フロー
トラブル時に慌てないため、行動をあらかじめ決めておくことが重要です。
安全確保
ハザード点灯
二次被害を防ぐ位置へ停車
救護・通報
負傷者の確認
必要に応じて119番通報
施設への報告
「いつ・どこで・誰が・何が起きたか」
家族への連絡
管理者判断のもと状況説明
④ 送迎ルートと時間管理
当日の欠席・追加利用の反映
工事・交通規制・天候(豪雨・積雪)への備え
無理のないスケジュール設定
時間短縮よりも 「安全第一」 を優先するルールを明記しましょう。
⑤ 接遇・コミュニケーション
ご家族への挨拶・情報共有
体調や様子のヒアリング
車内での安心感を与える声かけ
送迎は、事業所の印象を左右する重要な接点です。
3. 送迎業務チェックリスト(例)
カテゴリ | 確認項目 | チェック内容 |
車両 | 日常点検 | タイヤ・ライト・安全装置 |
介助 | シートベルト | 全員の着用・車椅子固定 |
情報 | 利用者名簿 | 欠席・特記事項の確認 |
安全 | 降車確認 | 車内最後部まで目視 |
4. よくある質問(FAQ)
Q:送迎中に体調が急変した場合は?
A:速やかに安全な場所へ停車し、施設へ連絡します。意識障害や強い症状がある場合は、迷わず119番通報を行います。
Q:家族不在で引き渡しできない場合は?
A:独断で利用者を残すことは避け、施設へ報告。マニュアルで定めた待機・連絡ルールに従います。
Q:置き去り防止装置が故障した場合は?
A:義務対象車両の場合、故障状態での運行は避けるべきです。管理者判断のもと、代替車両や代替確認手順を検討します。
まとめ|送迎マニュアルは「更新し続ける安全対策」
送迎マニュアルは、一度作って終わりではありません。
ヒヤリハットの共有
法令・ガイドラインの変更
現場の気づき
これらを反映し、定期的に見直すことが、利用者とスタッフ、そして事業所を守る最大の対策になります。

送迎業務の効率化を考えている方へ
送迎計画の作成やルート調整に時間を取られていませんか?
アビココが開発したAI自動配車システム「ナビれる」 は、送迎計画作成の負担を軽減し、現場が本来の介護業務に集中できる環境づくりを支援します。
車両1台あたり月額2,500円
先行登録100社限定・12ヶ月無料モニター実施中
初期設定無料代行あり
送迎業務の見直しを検討中の方は、ぜひ一度「ナビれる」をお試しください。
▼詳細・無料お試しはこちら
送迎の悩みはもう過去のものに。ナビれるで、あなたの施設の送迎業務を変えてみませんか?
アビココの会社案内や導入実績資料はこちらからご覧いただけます。
参考文献
さらに一歩踏み込んだ視点は、こちらの記事で解説しています。